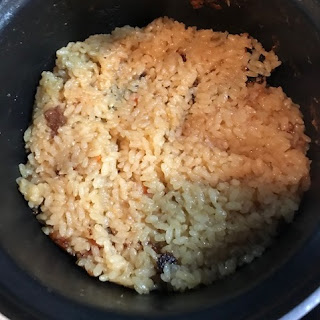本日のお題は『フットクラッチ』。
旧車のハーレーにはバエますよね〜☆
剥き出しのオープンプライマリーベルトにスーサイドクラッチにジョッキーシフトはチョッパー3種の神器!
私がレーハーに乗り出した『ショベルブーム時代』にはこのスタイルが定番でありました。
ズボンに少し隠れているダイヤが『シフトノブ』。
これを手でガチャガチャやってシフト操作をするからハンドシフト。
足でクラッチ操作をするからフットクラッチ。
つまり、通常の操作が逆さまになるワケです。ハイ。
いきなり標題に反しますが、特にオススメはしていません。
操作には一定の熟練度が必要だし、そもそもこうしなくても乗れます。
ただ、今見るとやっぱりカッコいいんです...。
単に操作を逆にしただけなのに、サービスエリアとかで走り出すと超視線を感じますw
また、最近一回りした効果か、やはり王道の強みか、フットクラッチ化のオーダーが入ります。
...そして、フットクラッチの乗り始めは多くのオーナーがその操作に手こずります...
フットクラッチの操作には慣れと言うコツがあるので最後に記しますね☆
まず、コチラが『スーサイドクラッチ』と呼ばれる構造です。
suicide【súːəsὰɪd(米国), s(j)úːɪd(英国)】
辞書で調べると米国人が好きそうな、ありがたくない意味でゲッソリしますが、『向う見ず』的な意味としても使われるらしいです。このクラッチとフロントブレーキレスのバイクをスーサイドセットアップとも呼び、米国人でもさすがに危ないということは知っていたワケなんですねww
通常はハンドルのクラッチレバーより伸びたクラッチケーブルがトランスミッションのレリーズアームを引きクラッチを切るワケですが、画像のようなフットクラッチの場合フットペダルからレリーズアームをシャフトでつなぎます。
単純にマニュアル自動車のようにクラッチペダルを踏むとクラッチが切れ、離すと繋がるという構造。つまり、ニュートラルを入れない限り、左足は地面に下ろせません。バランスを崩してうっかり左足を着くと...。エンストします。
ここがちょっと危ない所以なんだとは思いますが、よくあることです。エンストした時の対処のコツは、まず、異常に落ち着いたフリをする。後方車に少し挨拶をして、素早くニュートラルを出してから確実にスタンドを出し、キック始動する。ですかね。もし、始動性が安定しないコンディションのバイクなら路肩に寄せた方が迷惑になりません。
また、たまたま画像がありませんが、旧年式のハーレーが純正採用していた『ロッカークラッチ』と呼ばれるフットクラッチも存在します。スプリング式のフットクラッチがクラッチを切った状態で固定できることからロッカー。足の操作方向がスーサイドとは逆となり、シーソー状のペダルを、切るときはリア側に倒し、フロント側に倒しつつクラッチを繋げるという構造。
どっちが優れているのかよく議論になりますが、そもそも片手放しでシフト操作していることを思えば趣向性の問題とも言えます。
次にそのシフト操作です。
このシフトノブもいろんなデザインのものが販売されているので、選ぶのも楽しみ。このバイクにはマシュマロがついています。
このレバー位置でシフト操作をする様が、騎士が馬に鞭を入れることに似ていることからジョッキーシフトとネーミングされたとのこと。
操作方法は、通常足で、1-N-2-3-4 と操作しているのを手で前後に操作するだけ。1速の方向がFLとFXでは逆となります。がこれも生まれつきの個性くらいに考えて大丈夫です。
さらにトランスミッションのTOP構造が年式により異なり、メカニカルTOP、ラチェットTOP、ロータリーTOPの順で新しくなります。
ラチェットTOP。
ショベル1200後期頃まで採用されていました。 コチラがロータリーTOP。
画像のバイクはハンドクラッチです。
どちらもシフト操作後にはレバーが元位置に戻る構造です。操作感に違いがありますが、愛車をカスタムする場合はこれも我が子の個性という名の宿命と思って大丈夫です。
ラチェットTOP以前のメカニカルトップは、操作時にはレバーが1速、1速個々の位置へと移動します。純正パンヘッドのハンドシフトとか、タンクに切り欠きのついたステーがマウントしてあり、シフトそれぞれの位置が決まっていることを思い出すと理解できます。
また5speed後のミッショントップはさらに変更となります。
では、最後に巻頭でふれた操作のコツについて。
手こずるオーナーの多くの悩みが...
『発進時のクラッチの繋ぎ方』
発進するときに、バイクが『ズドンと飛び出してしまうのではないか?』と、『エンストさせたくない』2つの恐怖心がせめぎ合ってってしまい、なかなかスムーズにクラッチを繋げないのです。その場合スロットルの回転数だけがやけに吹かし気味になっていることが多く、そのままクラッチを繋げるとガクンというギャップを感じながら発進するか、エンストするかのどっちかとなります。
そのコツは、
【スロットルを回すより先に半クラを出すこと】
ハーレーには粘り強い“トルク”があります。
極端な例えですが、手がクラッチのバイクでも超ゆっくりクラッチを繋いでゆけばそのトルクの粘り強さにより、全くスロットルを開けなくても発進できちゃいます。
【その手順は】
『クラッチを踏んで、シフトノブを押し込んで1速を入れる』
☟
『踏んでいるクラッチペダルをゆっくりと戻す』
☟
【ココがポイント!】『次第にリアタイヤに動力が伝わる感覚を感じたら...』
☟
『さらにクラッチを戻す』ゆっくりと を同時に操作します。
『スロットルを開ける』
すると回転数とのギャップが少なく安全かつスムーズに発進できます。
イメージは『半クラに乗せていく』感じでしょうか?
でも、あらためて上の手順を見ると手のクラッチ操作でも全く同じなんですよね♪
普段は無意識にやれてしまっている操作を足で出来るようになる。がポイントですが、手でクラッチ操作をしている時もスロットルから先に開けている方はてこずるかもしれません。
お考えの方はお気軽にご相談ください☆
ベガスホームページへGO!
ベガス本店
販売車輌ショールーム&
サービス工場&カスタムペイント工房
TEL047-360-8190
open 10:00
※当日作業ご予約の開始時刻は10:30~
close 20:00
毎週水曜日定休
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷3471
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★